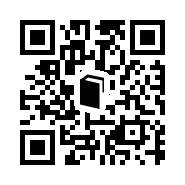中学生の一時期、ラジオ技術講座の通信教育を受けていたことがある。まぁ当時の通信教育なんで、あんまりいい印刷ではないテキストが数冊送られてきてそれを読んで勉強し、巻末だかにあるテストを切り取って答えを書き込んで送ると免状みたいなのが貰える、というだけのものなんだが。
一応修了したらラジオ製作キットの安いのを買って…と思ってるうちに少年の興味は音楽に移ってしまい、ラジオキットのために溜めていた小遣い(アルバイトもやった)は2万ナンボのフォークギターに化けることになったのだが、まぁそれはそれだ。オレが受けていた類いの通信教育、この本によれば日本の電子工業の発展に於てなかなかの役割を果たしてきたんですな。
1887年ヘルツによる電磁波の発見から筆を起こし、日本におけるラジオ放送の黎明、戦時下の電波による情報統制、戦後のラジオ工作ブームへと、オレが生まれる前の歴史が語られる。ラジオよりずっと難しいテレビ受像機に関しても、自作しようというアマチュアがたくさんいたというそのバイタリティにも驚くが、自分の体験してきた「カラーテレビの普及」の裏話には瞠目。
そしてトランジスタ・ラジオ。日本の高度経済成長の象徴ともなったあのトランジスタ・ラジオがアメリカで爆発的に売れたのは、プレスリーのせいであり元を辿れば彼が真似をしたブラック・ミュージック,ロックンロールであり、それらのメインストリームへの進出を阻んだ人種差別が遠因とも言える、という話も面白い。
その他にも日本でもアメリカでもオーディオは「オトコの趣味」だてな話(Hi-Fiなんて言葉ひさびさに見た、Wi-Fiぢゃないよ、Hi-Fiだよ)や数少ない女性技術者の逸話など面白い実話満載で読むのに結構時間がかかってしまったが、その時間分の価値はありましたよ。