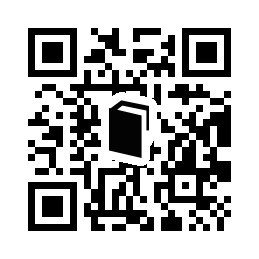変わった本である。タイトルの通り「発明」というものをテーマに,それがどのようにして始まるのかということに関して考察しているわけだが,それってどんなことか,想像がつきますか? 言葉にするのは簡単だが,では具体的にどんなことが書かれているのかということになると,ちょっと雲を掴むようなトコロ,あるでしょ?
著者の主張はこうだ。すべての「発明」は無から突然生み出されたものではない。たとえば飛行機,一般的には「ライト兄弟が発明した」ということになっているが,彼らが飛行機に関する技術のすべてを考え出したわけではなく,9世紀にベルベル人の科学者アッパース・イブン・フィルナースが製作した初歩的なグライダーから綿々と蓄積された発明・発見の蓄積の上に彼らがいる。
あるいは蒸気機関しかり。蒸気機関と聞くと我々は,半ば条件反射のように「ジェームズ・ワット」とその「発明者」の名前を口にし,ついでにそれを18世紀の産業革命に関連付ける。しかし歴史を繙けば紀元前1世紀,アレキサンドリアのヘロンは蒸気によってタービンを回転させる仕掛けを作っていた。蒸気機関の発明は,実質的には「熱力学の発明」であり,そして「スピードの発明」に連なって行く。
はたまた活版印刷。活版印刷と聞けばこれまた反射的にグーテンベルクの名前を挙げるヒトが多かろう。でもグーテンベルクは具体的に何を発明したのだろうか? 1文字1文字を刻んだ「活字」を組み合わせてフレキシブルな印刷を可能にした? そんなことは既に11世紀,遥かに文字数の多い中国で実用化されている。そもそも印刷技術の発明は,紙の発明なしにはあり得なかった。
こうした考え方を元にして,著者はインベンション(発明)を,ある人が行ったある1つの創造的な行為と定義し,それらが数多く集まって生み出された果実を,マルチジェニウム(多元産生)と呼んで区別する。そしてインベンションが集まってマルチジェニウムが形作られるプロセスを描き出す。いわゆる「発明者」は,その創造的行為というそのプロセスの中で,臨界点…発明や技術がひとつのエポックに結実するときに登場した「優れた典型」なのだ。
うーん,ここまで書いて読み返してみると,ちっともこの本の面白さを伝えられていないような気がする。テーマはともかく,斯くの如き結論を導き出すために著者が集めてきた発明・発見・技術革新に関するエピソードのあれこれが,なんつうかとんでもなく目ウロコものなのよ。
一個だけ例を挙げよう。アルファベットの「大文字」をアッパーケース,「小文字」をロウワーケースって言うでしょ? あれってグーテンベルクの印刷機を使う植字工がローマン体(大文字)の活字の入った引き出しを,カロリング体(小文字)の活字の引き出しの上に置いて区別したことから来ている呼び名なんだと。この本,そんな話が満載なんです。どっすか?